NPB(日本プロ野球)とMLB(メジャーリーグ)では、
トレードに関するルールや文化が大きく異なります。
毎年夏の時期になると、MLBではトレードの話題が盛り上がりますが、
NPBではシーズン中に大きなトレードが起きることは非常に少なくなっています。
本記事では、NPBファンの方向けに
「MLBのトレード制度」の基本について、実例を交えながら解説していきます。
また、当ブログではMLB初心者の方向けに
MLBをより楽しむための基本的な制度解説や球団の特徴分析などを行っています。
下記のおススメ記事についても、ぜひ目を通していただけると嬉しいです。
・【NPBファンのためのMLB入門】まずはここから!!シーズンの流れに沿ってMLBを徹底解説!
・【球団分析:ア・リーグ西地区編】球団の特色や主力選手をMLB初心者向けにわかりやすく解説!!
まず初めに「トレード」について、NPBとMLBの主要な違いを一覧表で見てみましょう。
| 項目 | MLB(メジャー) | NPB(日本プロ野球) |
|---|---|---|
| シーズン中のトレード期限 | 毎年7月末頃 (7月28日〜8月3日の間で設定) | 毎年7月31日 |
| トレードの規模・頻度 | 年間数十件規模。複数球団・複数選手が絡む大型トレードも頻繁に発生 | 年間数件程度。基本は2球団間で1対1や2対2程度の小規模な移籍 |
| 交換できる内容 | 選手(メジャー・マイナー問わず)金銭、特定のドラフト指名権、 国際FA契約のボーナス枠など | 選手(支配下選手・育成選手)、 金銭 |
| トレード拒否権 | 一部選手にあり (契約でノートレード条項、または10年/5年在籍で自動発生) | なし(球団の裁量で移籍可能) |
| 文化・傾向 | 移籍は日常茶飯事。成績不振球団は再建のため主力放出も辞さない。 | 移籍は稀。有望選手を長く囲う傾向が強く、大物のシーズン中移籍はほぼない。 |
トレードの基本ルール(期限・対象・手続き)
トレードとは球団同士が選手の契約保有権を交換する制度です。
MLB・NPBともにオフシーズンおよびシーズン中にトレードが可能ですが、
シーズン中には期限(トレード・デッドライン)が設定されています。
トレードの期限
- MLBのトレード期限
毎年7月末頃に定められており、週末を避けるために年度によって若干日程が前後します。
デッドラインを過ぎると、その年のシーズン中は
選手を他球団へトレード移籍させることが一切できなくなります。 - NPBのトレード期限
毎年7月31日となり、これ以降シーズン終了までは球団間のトレードが一切禁止されています。
シーズン後半に移籍できない点はMLB・NPB共通ですが、
MLBではこのデッドライン直前に、毎年大量のトレードが実施されます。
締切当日に十数件ものトレードが駆け込みで成立することも少なくありません。
トレード対象の選手と三角トレード
トレードの対象になるのは原則として球団の契約下にある選手です。
MLBではメジャー登録されている選手だけでなく、マイナー契約の選手もトレードの対象になります。
NPBでも同様に、一軍・二軍問わず支配下登録されている選手や育成選手が対象となります。
MLB独自の特色として、複数の球団間で同時に選手を交換する「三角トレード」も珍しくありません。
NPBでも1980年代に三角トレードが実施されたことがありますが、
その実態は2球団間のトレードを同時に複数発生させたというものになっています。
(例)
A球団のa選手 ⇔ B球団のb選手
B球団に移籍したa選手 ⇔ C球団のc選手
★結果 A球団:b選手 B球団:c選手 C球団:a選手
また、トレード手続きは球団間の合意で決まり、選手本人の意思は関与しません。
(後述するトレード拒否権を持つ場合を除きます)。
トレードで交換されるもの(選手以外の要素)
トレードは主に「選手と選手の交換」が基本にはなりますが、
MLBではそれ以外の要素も取引材料となります。
①金銭(キャッシュ):
一方の球団が金銭を支払ってその選手を譲り受けることがあります。
②ドラフト指名権:
MLBでは一部のドラフト指名権をトレードに含めることが認められています。
ただし1巡目指名権など大半の指名権はトレード禁止で、
例外的に戦力均衡ラウンドの指名権のみ交換可能です。
※「戦力均衡指名権(Competitive Balance Pick)」とは、
MLBにおいて、収益や市場規模の小さい球団に与えられる追加のドラフト指名権です。
MLB機構が指名権の付与を行っており、球団間の戦力格差を抑えることを目的としています。
1巡目指名終了後に行われることが一般的です。
③海外FA契約のボーナスプール枠:
MLBには海外出身のアマチュア選手と契約する際に使える
「国際ボーナスプール枠」という予算枠が球団ごとに定められています。
このボーナス枠の一部をトレードに使用することが可能です。
将来有望な中南米の若手選手と契約したい球団が、
他球団からボーナス枠を譲ってもらうためにマイナー選手を放出するといったケースが見られます。
【締め切り間近の駆け込みトレード】
MLB特有の仕組みとして、「Player To Be Named Later(後日指名選手)」があります。
デッドライン間際の駆け込みトレードでは移籍させる具体的な選手を決めきれない場合に、
「後日指定する選手○名を渡す」と取り決めておき、一定期間内(通常シーズン終了まで)に
相手球団へ渡す選手を指名する方式です。これにより締切までに合意だけ先に済ませ、
細部の調整は後から行うことができます。
トレード拒否権(ノートレード条項と10-5ルール)
『トレード手続きは球団間の合意で決まり、選手本人の意思は関与しない』とお伝えしましたが、
MLBには一部の選手にトレードを拒否する権利(=ノートレード権)が認められています。
大きく2つのケースがあります。
①契約によるノートレード条項:
スター選手との大型契約では、契約書に「トレード拒否条項」を盛り込むことが一般的です。
契約期間中は本人の承諾なしにトレードできないという条項を契約に盛り込むことで、
選手が望まない移籍を防ぐためものです。
②10-and-5 ルール(自動的な拒否権):
MLB独特の権利として、メジャー在籍10年以上かつ直近5年間同一チーム所属の選手には、
自動的にトレード拒否権与えられます。
これを「10-and-5 rights(テン・アンド・ファイブ)」と呼びます。
該当選手は契約条項に明記がなくても自分の意思でトレードを拒否できるようになります。
一方NPBでは、契約上ノートレード条項の制度はありません。
選手は球団の判断でトレードされる可能性があり、契約上それを拒む正式な権利はありません。
MLBではトレード拒否権を持ちながらも、自らそれを放棄して移籍を志願する選手もいます。
例えばイチロー選手(マリナーズ在籍11年目当時)は10-and-5のトレード拒否権を得ていましたが、
チーム再建のため自らトレードを直訴して拒否権を行使せず、ヤンキースへの移籍が実現しました。
逆に契約上のノートレード条項を駆使して行き先を選んだりトレード自体を拒む選手もおり、
希望の球団にのみ移籍を認めた例などがあります。
こうした駆け引きも含めて移籍劇のドラマになるのがMLBならではと言えるでしょう。
トレードの目的と文化:MLBはなぜトレードが多い? NPBは少ない?
トレードの基本的な制度設計を確認したところで、
「MLBではなぜこれほどトレードが活発なのか?」について考えていきたいと思います。
そこにはリーグの制度上の違いと文化・慣習の違いが絡んでいます。
それぞれの観点から理由を見ていきます。
制度面から見た違い(戦力補強戦略の幅)
MLBのトレードの目的は大きく分けて2つあります。
①優勝争いに向けた戦力補強(買い手) ②将来を見据えたチーム再建(売り手)
シーズン中盤に差し掛かった段階で、
球団によっては「地区優勝やプレーオフ進出の可能性が薄い」状況が発生します。
そうした球団は翌年以降の立て直しのため、
主力選手を放出し、代わりに将来有望な若手選手(プロスペクト)を獲得します。
これが「②将来を見据えたチーム再建(売り手)」に該当します。
一方、優勝を狙える上位チームは有望な若手選手と引き換えに即戦力のスター選手を補強し、
シーズン後半〜ポストシーズンに臨む力を充実させます。
こちらが「①優勝争いに向けた戦力補強(買い手)」に該当します。
いわば「今と未来の価値交換」が行われるのがMLBのトレード市場の特徴です。
例えばシーズン7月に入ると、
「〇〇球団は主力選手の大売り出し(ファイヤーセール)に踏み切るか?」とか
「△△球団は先発投手をもう1枚買いに行くか?」といった報道が飛び交います。
球団間で**買い手(Buyer)と売り手(Seller)**に分かれ、
短期的な戦力 vs 将来の戦力のトレードが活発化するのです。
そのためMLBでは、夏場にチームの主力級選手ですらトレードされることが珍しくありません。
特に主力選手が今シーズンでFA権を取得し、オフの流出が濃厚な場合には
下位球団が当該選手をシーズンオフまで保有するメリットが無いため、
積極的なトレードが敢行されます。(後述するレンタルトレードに当たります)
つまり、MLBのFA権がNPBと比較して
短期間で取得可能(初回6年/2回目以降は現在の契約が切れ次第FA)で、
かつ宣言するのではなく、自動的に行使されるという選手の流動性の高さが
トレードによる移籍もより活発化させているとも言えます。
一方NPBの場合、FA権の取得に国内FA8年、海外FA9年と長期間を要します。
かつMLBとは異なり、2回目も同様に5年という長期間を要する仕組みになっています。
そのため、そもそも主力選手がFA権を取得するというケース自体が少なく、
かつ、NPBではFA流出時に「人的補償」や「金銭補償」という見返り制度があるため、
敢えてトレードで放出するメリットが薄いという事情もあります。
さらには年俸・契約面の違いもあります。
MLBではスター選手の年俸が数十億円規模に達し、契約年数も10年超の超大型契約が存在します。
球団としては高騰するサラリーを嫌ってトレード放出し、
代わりに年俸の安い若手複数名と入れ替えるケースがしばしば見られます。
以上のように、MLBは制度上「短期戦力と将来資産の交換」が合理的に成立する環境であり、
NPBは制度上もそれが起こりにくいと言えます。
文化・慣習から見た違い(選手と球団の考え方)
制度面以外に、日米の野球界における文化や価値観の違いも移籍の活発さを左右しています。
NPBでは、引退まで同じチーム一筋でプレーし、選手生命を全うする選手は
ファンからレジェンドとして愛される傾向にあります。
そのため球団側も生え抜きの功労者を大切にし、できるだけ他球団へ放出せず、
自球団に置こうとする傾向があります。
対してアメリカ(MLB)では、移籍は当たり前という価値観が浸透しています。
選手にとっても「契約が切れればより良い条件を求めて移籍するのは当然」であり、
ファンもそれを受け入れています。むしろMLBでは各選手のキャリアで複数球団を渡り歩くのが普通で、一つのチーム一筋で活躍する選手の方が稀です
また、NPBではトレードは「戦力外通告に近い」とネガティブに捉えられる場合があります。
元のチームで居場所を失ったというイメージが付きまといやすいのです。
一方MLBではむしろ「必要とされて他球団が獲得した」というポジティブな捉え方もされます。
優勝争いをするチームに求められた結果として移籍するのであれば、
選手にとっては評価されている証拠であり、名誉とも言えます。
実際、シーズン中のトレードで移籍した選手が新天地で活躍し
チャンピオンリングを手にする例も数多く、
ファンも「この移籍でチームが強くなるなら歓迎」と比較的前向きです。
FA/トレードといった移籍が、野球シーンの一部として日常に溶け込んでいると言えるでしょう。
レンタルトレードとは?仕組みと有名な事例
最後にMLBの会話の中でよく聞かれる「レンタルトレード」について解説します。
レンタルトレードとは、契約が残りわずか(シーズン終了後にFA権取得や契約満了)となった選手を
短期間“レンタル”するような形でトレード獲得することを指します。
シーズン終了後にはその選手がフリーエージェントとなって離脱する可能性が高く、
主に優勝を狙う強豪チームが、今季限りで契約切れになる
他球団のスター選手を獲得するケースで使われる表現です。
ただし、実際に「レンタル移籍」という公式制度があるわけではなく、
あくまでファンの間やメディアでの俗称です。
サッカーでよく聞かれるレンタル移籍は
現在の所属チームで契約した状態のまま、他のチームでプレーする制度のため、
呼称は同じでも全く異なる性質を持ちます。
レンタルトレードでは移籍先チームは短期的な戦力アップを得られ、
放出側チームは将来の有望な若手を見返りとして得られます。
選手本人はシーズン後にFAとなり高額契約を結ぶ機会を手にするか、
元の古巣に出戻るケースもあります。
以下にMLBで特に有名なレンタルトレードの事例をいくつか紹介します。
- 2016年:アロルディス・チャップマン投手(ニューヨーク・ヤンキース → シカゴ・カブス)
ヤンキースの守護神チャップマンはその年限りでFAとなる状況でした。
ワールドシリーズ制覇を目指すカブスはチャップマンを獲得。
ヤンキースは当時19歳の超有望株グレイバー・トーレス選手ら若手4人を獲得しました。
チャップマンはカブスで期待に応えチームを108年ぶりの世界一に導きます。
そしてオフになるとFAとなったチャップマンは古巣ヤンキースと再契約し、
結果的にヤンキースは有望な若手選手を手にしつつエースリリーフを取り戻す形となりました。
短期間の在籍でもたらした絶大な成果から、
このトレードは典型的な「レンタル移籍」の成功例として語られます。
- 2017年:ダルビッシュ有投手(テキサス・レンジャーズ → ロサンゼルス・ドジャース)
ダルビッシュ投手もシーズン終了後にFAを控えていたため、
当時所属していたレンジャーズが7月末に放出を決断しました。
ポストシーズンに向け先発投手を欲していたドジャースが複数のプロスペクトと引き換えに獲得。ダルビッシュ投手はその後のリーグ優勝に貢献しましたが、
ワールドシリーズ制覇にはあと一歩届かず、シーズン後にFAとなって翌年カブスへ移籍しました。短期間とはいえ名門ドジャースでエース級の活躍をした姿はファンにも強く印象に残っています。
- 2018年:マニー・マチャド選手(ボルチモア・オリオールズ → ロサンゼルス・ドジャース)
オリオールズの看板打者マチャドもFA直前の夏にトレード放出されました。
争奪戦の末ドジャースが獲得し、マチャドはシーズン後半~ポストシーズンで主力として活躍。
オフに彼はFAとなり、サンディエゴ・パドレスと10年超の超大型契約を結んで移籍しました。
わずか数か月の在籍ながらリーグ優勝に貢献したことで、
ドジャースにとっても「レンタル成功」の一例と言えるでしょう。
- 2020年:ムーキー・ベッツ選手(ボストン・レッドソックス → ロサンゼルス・ドジャース)
ベッツの場合はシーズン途中ではなくオフシーズンの大型トレードですが、
本質的には契約残り1年のスター選手を放出した例として注目されました。
年俸総額削減と将来戦力の確保を図りたいレッドソックスが、
当時27歳でMVP経験者のベッツをドジャースへトレード。
移籍後ベッツはドジャースと長期延長契約を結び、その年のワールドシリーズ制覇にも貢献。
結果的にレッドソックスは1年後にFAで失う可能性のあった選手からプロスペクトを獲得し、
ドジャースはスター選手を長期契約で手中に収めた形です。
この取引は「大型契約前提のレンタル」ともいえる特殊な例ですが、大きな話題になりました。
- 2022年:フアン・ソト選手(ワシントン・ナショナルズ → サンディエゴ・パドレス)
ソトは当時23歳という若さで首位打者や本塁打王争いにも絡むスーパースターでした。
彼は契約上FAまで2年以上残っていましたが、
ナショナルズとの延長契約交渉が決裂したことを受けてシーズン途中に電撃放出されました。
パドレスが歴史的とも言われる規模の有望株パッケージ(プロスペクト複数名+若手主力)を差し出してソトを獲得し、将来の優勝を見据えた大型補強となりました。
MLBでは将来の契約を見通し、若手選手でさえも
トレードに出される可能性があることを象徴する出来事でした。
おわりに
MLBとNPBのトレード制度・文化の違いについて、主要なポイントを解説しました。
MLBではトレードがリーグの一大イベントとして毎年盛り上がり、
主力選手の電撃移籍や複数球団を巻き込んだ大型トレードがしばしば起こります。
ファンも「移籍も含めて野球の楽しみ」と捉えており、シーズン中もオフも話題が尽きません。
一方でNPBでは移籍は少数で慎重に扱われ、
長年同じチームで活躍する選手を応援できるのが魅力でもあります。
それぞれの良さがありますが、MLB楽しむ際には、
ぜひトレード市場の動きにも注目してみてください。
選手移籍のドラマを知ると、より深くメジャーリーグの世界を楽しめるはずです。
当ブログではMLB初心者の方向けに
MLBをより楽しむための基本的な制度解説や球団の特徴分析などを行っています。
下記のおススメ記事についても、ぜひ目を通していただけると嬉しいです。
・【NPBファンのためのMLB入門】まずはここから!!シーズンの流れに沿ってMLBを徹底解説!
・【球団分析:ア・リーグ西地区編】球団の特色や主力選手をMLB初心者向けにわかりやすく解説!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
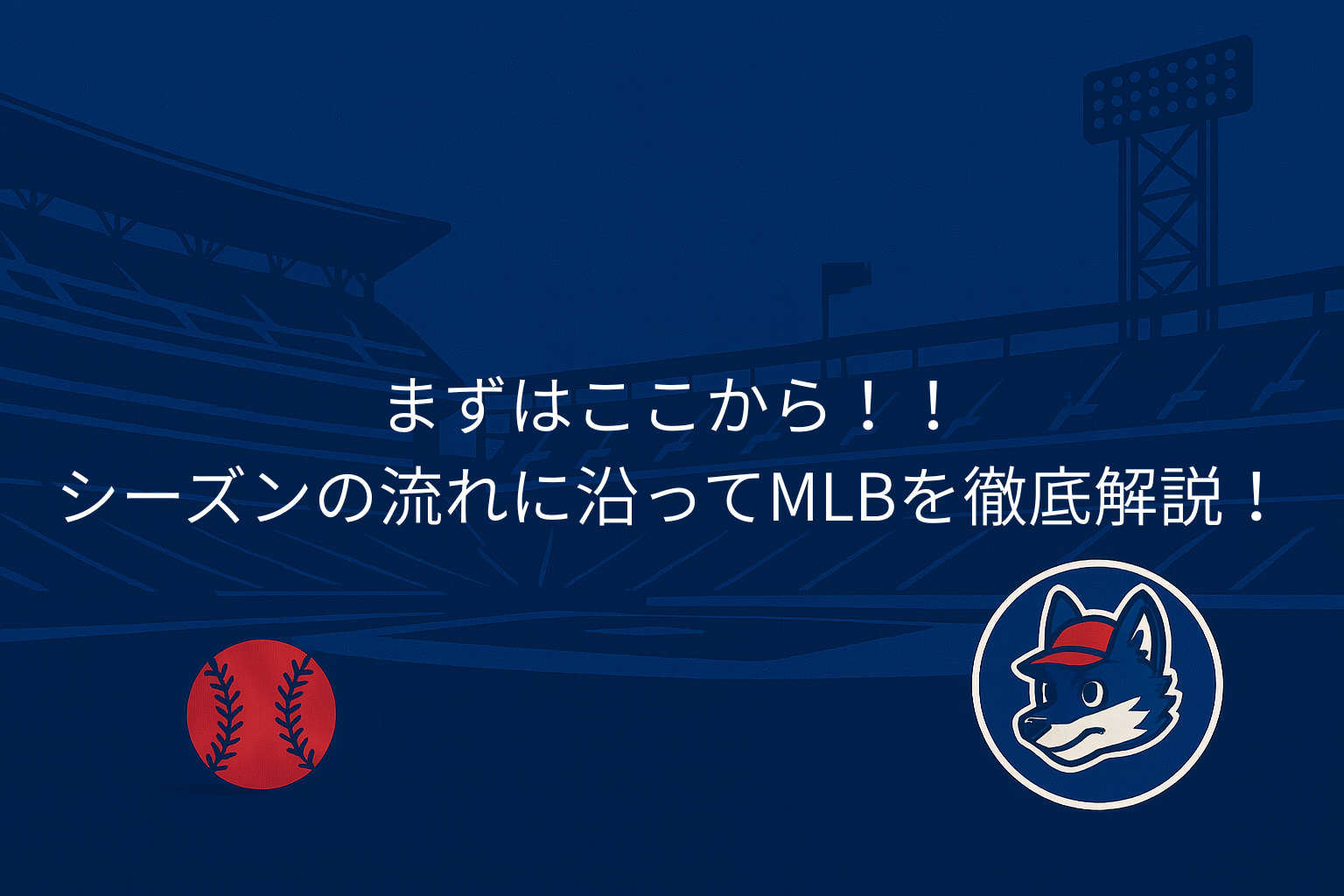
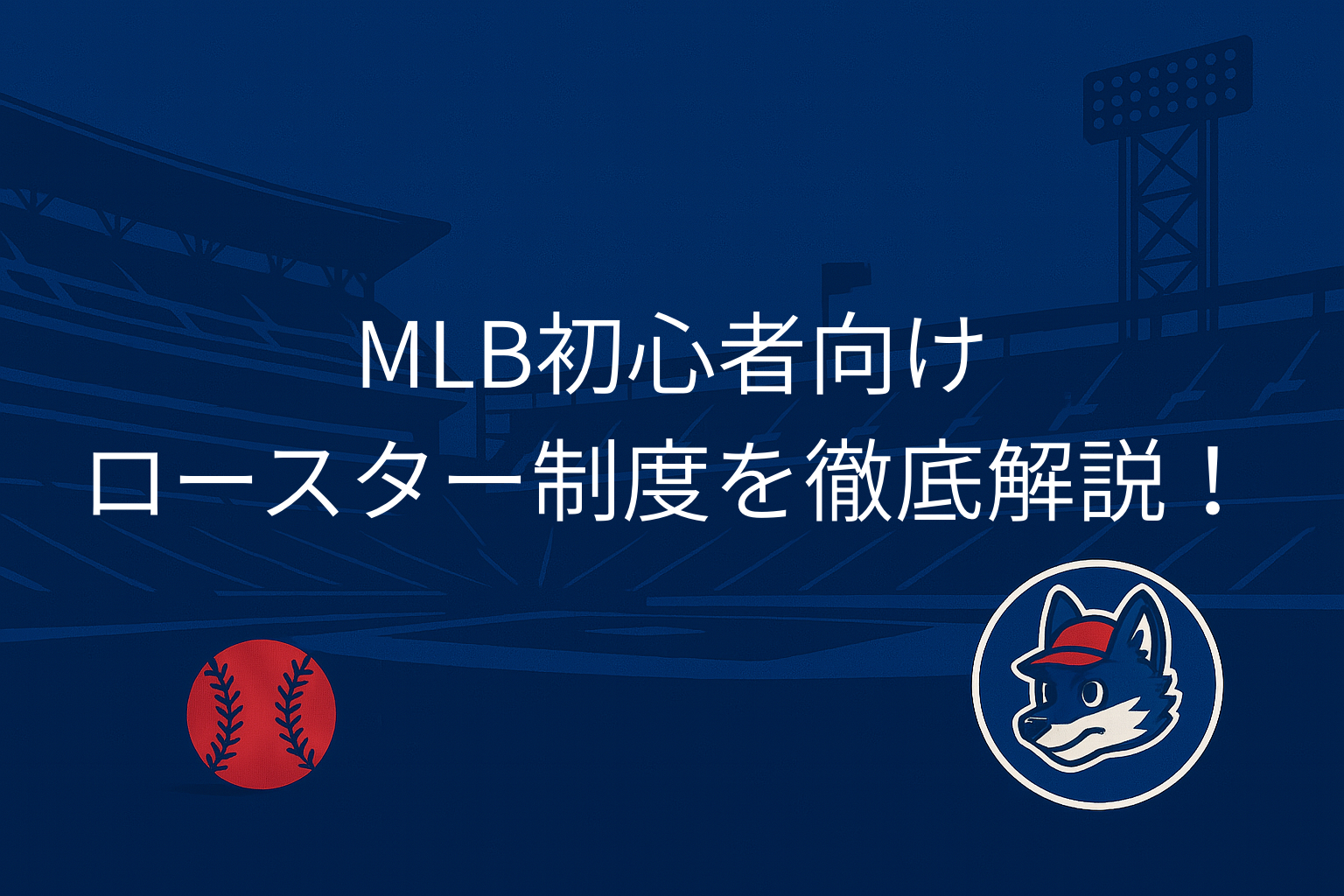

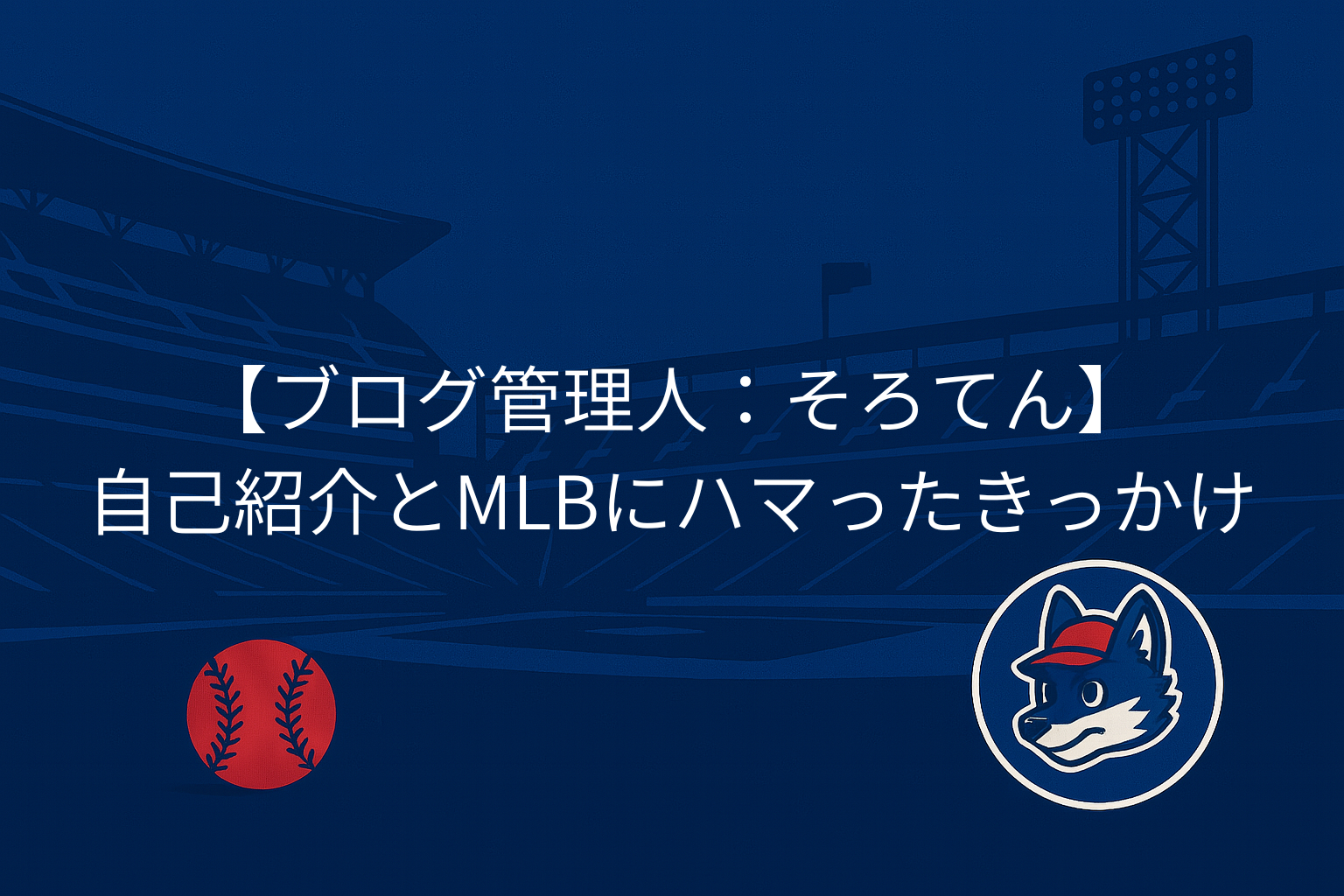

コメント