「ライフラインが止まったら、自宅でどうやって生活を続ける?」
大規模な地震や台風の直後、自宅に大きな被害がなければ「在宅避難」という選択肢があります。避難所に行かず、自宅で生活を続けることができる反面、電気・ガス・水道といったライフラインが止まると、一気にサバイバル状態に。避難所生活は心身ともに疲労する可能性が高いため、自宅避難ができるようにしっかりと準備しましょう。
防災リュックが“逃げるための道具”なら、備蓄は“家にとどまって生き延びるための準備”です。
今回は防災シリーズ第2回として、自宅で災害後を乗り切るための「備蓄」について、量・道具・食品の3つの視点から詳しくご紹介します。
1人あたりの備蓄量の目安
まずは家族1人あたり、最低限どのくらい備蓄しておけばいいのか、基本の目安を確認しておきましょう。
- 水:1人1日3リットル × 7日分 → 合計21リットル
- 食料:1人1日3食 × 7日分 → 合計21食
一般的には「最低3日分の備蓄」が推奨されていますが、災害の規模や復旧までの時間を考慮すると1週間分の備蓄が安心です。特に赤ちゃんや高齢者のいる家庭では、多めの準備を心がけましょう。
ライフラインが止まった時の「暮らしを回す道具」
食料や水があっても、「火を使えない」「調理できない」「洗い物ができない」となると生活は非常に不便になります。以下の道具は、災害後の在宅生活を回していくために不可欠です。
- カセットコンロ:電気やガスが止まっても、温かい食事やお湯を確保できます。1家庭に1台は必須。
- カセットガスボンベ:1本で約1時間使用可能。1人あたり3〜5本を目安に備蓄しましょう。
- 紙皿・紙コップ・割り箸:洗い物ができない前提で、使い捨て食器があると便利です。
- ラップ:皿に巻いて使うことで、何度も使える工夫に。
- 簡易洗浄スプレー:水が使えない時の皿拭きや手洗い代用に。
おすすめの備蓄食品
備蓄食品のポイントは、「調理が不要」「常温保存できる」「賞味期限が長い」こと。そして、できれば「家族が普段から食べ慣れているもの」であることが重要です。以下にジャンル別でおすすめ食品をご紹介します。
ごはん系
- アルファ化米:水やお湯を入れるだけでご飯ができる。長期保存可能。
- レトルトおかゆ:体調不良時や高齢者にも食べやすくおすすめ。
主菜系
- 缶詰(さば・焼き鳥・ミートボールなど):温めなくてもそのまま食べられる。
- レトルトカレー・ハヤシ:温めれば満足感あり。ご飯とセットで備蓄。
パン・主食系
- 缶入りパン:ふわふわ感が長期間保てる。子どもにも人気。
- クラッカー・乾パン:噛み応えがあり、非常時の満腹感に役立ちます。
おやつ・軽食
- ようかん・ゼリー飲料:エネルギー補給+水分補給も兼ねる。
- チョコレートや飴:気持ちを落ち着ける効果もあり、災害時のストレス軽減に。
飲料・水分補給
- ミネラルウォーター:500ml〜2Lを複数本。保存水は5年程度持つタイプも。
また、家族にアレルギーがある場合は対応食品を、赤ちゃんがいる場合は粉ミルクや離乳食も忘れずに備えておきましょう。
ローリングストックで無理なく備える
備蓄を習慣化するコツが「ローリングストック」。日常的に使う食品を少し多めに買って、使った分だけ補充するサイクルを作れば、賞味期限切れも防げて一石二鳥です。
防災用品=特別なものと思わず、「普段使っている食品を非常時にも使う」発想で備蓄を始めてみましょう。
次回予告|お家の防災|地震発生の瞬間、どう生き延びる?
防災シリーズの次回は「お家の防災」がテーマ。家具の固定や非常時の安全スペースの確保など、地震が発生した“その瞬間”に命を守る備えをお届けします。
「備蓄」は今すぐ始められる命の備えです。今日の買い物から、できることを1つずつ始めていきましょう。

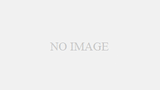

コメント